\30分で課題が見える/
無料で使える生成AI5種類を徹底比較!SEO記事の見出し構成を作らせてみた結果

- 「ライティングに使う生成AIは「ChatGPT」「Gemini」とか沢山あるけど、どれがいいの?」
- 「無料のままで果たして使い物になるの?」
このテーマは、いま多くのWeb担当者が最も気になるポイントでしょう。
そこで今回は、ChatGPT(GPT-5)/Claude Sonnet 4/Gemini 2.5 Pro/Copilot/Gensparkの5種類に、同じプロンプトを与えて「AIライティングはSEOに有効か」という記事の見出し構成を作らせました。
それぞれのAIがどんな見出しを作ったのか、評価はどうだったのか。実際に比較してみると、AIごとの個性や強み・弱みが浮かび上がってきました。
本記事では、その比較結果と総合評価をまとめています。
最後には、手直しした完成形の見出し構成も紹介していますので、生成AIを記事作成に取り入れたい方の参考になるはずです。
早速「各生成AIがつくった見出し構成の比較」が気になる方は、次のボタンで移動できます。
無料で記事作成に使える生成AI【5種類を比較】

生成AIは数多く登場していますが、ここでは特に記事作成に役立つ5つの主要サービス ― ChatGPT(GPT-5)/Claude Sonnet 4/Gemini 2.5 Pro/Copilot/Genspark ― を取り上げます。
今回は、あくまで無料プランで使える生成AIの比較です。
それぞれ「どの会社が作っているのか」「本来の得意分野」「無料で使える範囲」「有料プランで広がる部分」を整理しました。
ChatGPT(GPT-5)|OpenAI
アメリカのOpenAIが開発した代表的な生成AIです。自然な日本語表現や構成力に優れ、ブログ記事や比較記事の作成にも安定して利用できます。
無料プランでも現時点最新のGPT-5を使えますが、利用回数や長文処理には制限があります。
無料で使える目安
| モデル/条件 | メッセージ数の目安 | 時間枠 |
|---|---|---|
| 高度モデル(GPT‑5 / GPT‑4) | 約 10メッセージ前後 | 3〜5時間 |
| 同じ条件でも、長くない/簡単な質問・返答中心なら | 20〜50メッセージ前後 | 3〜5時間 |
| 超簡単な使い方(短文の質問と答えを繰り返すなど) | 少なくて 5 メッセージ台から制限されることも | 3〜5時間 |
この制限に達すると、GPT‑5が自動的に軽量モデル(例:GPT‑5 mini)に切り替わることがあり、応答の精度や深さが若干下がると感じるかもしれません。
有料プランにすると、Thinkingモードや長い文脈処理が解放され、応答の速度や安定性も向上します。
Claude Sonnet 4|Anthropic
Anthropic社(アメリカ)が開発。自然な日本語の理解力や構成力に優れ、文章作成や比較記事、アイデア出しなど幅広く活用できます。
無料プランでも最新のClaude Sonnet 3.5やClaude 3系統を利用できますが、利用回数や長文処理には制限があります。
ただし利用回数や深い推論モードは制限されており、有料にするとExtended Thinkingや長文対応が強化されます。
Gemini 2.5 Pro|Google
私はGoogleが開発した生成AIであり、無料の「Gemini」ウェブ版を通じて多くの方にご利用いただけます。
自然な文章生成や多言語対応に強みを持ち、ブログ記事の作成から企画のブレインストーミングまで幅広い場面で活用可能です。
無料プランでも「Gemini 1.5 Pro」を使えますが、利用にはいくつかの制限があります。
| モデル/条件 | メッセージ数の目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| Gemini 1.5 Pro(無料版) | 利用回数に上限あり(非公開・変動制) | 通常の質問や記事作成なら十分対応 |
| 短め・簡単な利用 | 多めにやり取り可能 | 軽いQAや翻訳タスク中心 |
| 複雑・長大なタスク | 制限がかかる場合あり | 応答の質や速度が落ちることも |
無料のGeminiは「文章作成」「翻訳」「アイデア出し」などライトな用途には十分対応。ただし「長文処理」「複雑な推論」「高速性」が必要な場合は、有料プランへの切り替えが適しています。
Copilot|Microsoft
Microsoft が提供する生成AI「Copilot」は、Web・スマホ・Edge拡張など多様な環境で利用でき、日常の調べものから文章生成まで幅広く活用できます。
本来、AIライティングに特化している生成AIとは言い難く、資料作成等に強みを持っています。
無料版でも基本的なAIチャットや画像生成を試すことができますが、有料の Copilot Pro と比べると制限があります。
| 機能 | 無料版 |
|---|---|
| Microsoft 365 アプリ連携(Word, Excel, PowerPoint など) | 一部制限あり |
| GPT-4 Turbo の優先利用 | 利用不可 |
| 画像生成回数 | 制限あり(例:15回/日) |
| 商用利用 | 非推奨 |
| カスタムGPT(高度なカスタマイズ) | 利用不可 |
Genspark(ジェンスパーク)
元Baidu幹部らが立ち上げたスタートアップが提供するAI検索サービスです。
Genspark は AI 検索エンジン+生成AIの要素を持つツールで、基本機能は無料で利用できますが、検索量や速度、APIやチーム利用などの拡張は有料プランでの提供が予定されています。
| 制限内容 | 詳細 |
|---|---|
| クレジット制限 | 無料プランでは「1日あたり200クレジット」が与えられており、利用する機能や処理が重いものほどクレジット消費が大きくなる。 |
| 使えるエージェント・ツールの制限 | 高度な AI エージェントや一部ツールへのアクセスは有料プランのみ。無料版では限定的なものだけ。 |
| 機能の重さへの制約 | 複雑・大規模なデータ分析、動画生成などクレジット消費が大きい処理は、無料プランだと頻繁には使えない。 |
| リセットタイミング | クレジットは毎日自動的にリセットされる。なので、その日の上限を使い切ると、有料版でない限り“その日は重めの作業ができない”ことがある。 |
生成AIごとの見出し構成の比較
今回は5つの生成AIに「AIライティングはSEOに有効か」をテーマに記事を書いてもらいます。
ちなみに全く使っていないGmailアカウントでそれぞれの生成AIを利用するため、カスタマイズされていないフラットな状態で利用します。
まずは、以下のプロンプトで見出しを作ってもらいます。
■記事を執筆するプロンプト
あなたはSEOライターとして20年間務めています。
WEBマーケティングについて発信する「WORLDLINK」のWEBサイトで、
中小企業向けにSEOに関するブログ記事を執筆します。
以下の条件でSEOを意識した見出しを作成してください。
## 構成
見出し2はh2
見出し3はh3
見出し4はh4
で書いてください。
## 記事のテーマ
AIライティングはSEOに有効か
## 記事の目的・用途
SEOによる集客
## 想定読者
30代のWEB担当者
## 記事のトーン・文体
フォーマルですが、中学生でもわかるような平易な文章にしてください。
また、ですます調を基本にしてほしいものの、リズムのある文章にしてください。
## その他の要望
・SEOのプロとして一次情報となる独自の見解を具体的に入れて下さい。
・外部の数値データは積極的につかってください。ただし、公的機関や信頼のおける客観的期間のみです。ChatGPT
評価:
h2:AIライティングとは何か:SEOとの関係を理解する
h3:AIライティングの定義と種類
h4:自動文章生成(テンプレート型/GPT型)の違い
h4:AIツールの導入事例(国内外の中小企業)
h3:SEOの基礎:検索エンジンが評価する要素
h4:コンテンツの品質(E-E‑A‑T、オリジナリティ、信頼性)
h4:キーワード最適化と検索意図(ユーザーインテント)
h2:AIライティングはSEOに有効か:メリットと限界
h3:メリット
h4:作業効率向上とコスト削減の実績
h4:継続的なコンテンツ量確保によるサイト力強化
h3:限界・リスク
h4:オリジナリティの欠如と重複コンテンツ問題
h4:誤情報・倫理的問題のリスク
h2:信頼できるデータから見るAIライティングの効果
h3:公的機関・研究機関の調査結果
h4:検索順位への影響を示すデータ(例:Google発表や学術研究)
h4:ユーザーの行動変化(滞在時間・直帰率)に関する統計
h3:筆者(SEOプロ)として見た現場での具体的な変化
h4:本文品質改善による検索流入ジェネレーションの増加率(事例付き)
h4:AIライティング導入後のメンテナンスコストとの比較
h2:AIライティングをSEOで有効に使うための実践ガイド
h3:導入前の準備:指針とルール作り
h4:社内ガイドラインの整備(スタイル・信頼性・著作権)
h4:キーワード調査と検索意図の共有
h3:執筆プロセスの最適化
h4:草稿をAIで作成 → 編集者が推敲する流れの設計
h4:AIだけに頼らず、人間の視点で付加価値を与える工夫
h3:SEOとの連携と成果測定
h4:Google Search Console・Analyticsでの指標の見方(順位・CTR・滞在時間)
h4:改善サイクルを回すためのKPI設定
h2:将来予測:AIライティングとSEOの今後
h3:検索エンジンのアルゴリズム更新の動き
h4:AI生成コンテンツの取り扱いに関するGoogleの立場(ポリシーの変化)
h4:ユーザー体験(UX)の重視のさらなる高まり
h3:中小企業が採るべき戦略
h4:差別化ポイントの強化(専門性・地域性・ストーリー性)
h4:人的リソースとAIツールのハイブリッド運用モデル
h2:まとめ:AIライティングはSEO投資として価値があるか
h3:要点の整理
h3:導入判断のチェックリスト(中小企業向け)構成は全体として「AIライティングはSEOに有効か?」という疑問に、AIライティングの概要 →メリットとリスク → データによる裏付け → 実践ガイド → 将来予測 → まとめ、という流れで答えており、一見するといい構成のように思います。
しかし、冒頭の「AIライティングとは何か:SEOとの関係を理解する」という見出しは明確に悪い点です。
ユーザーが求めているのは「有効かどうか」の答えであり、AIライティングの定義や基礎説明は既にクリアしているユーザーである確率が高いです。
このようなユーザーの検索意図と離れた見出しは離脱を招きます。
記事タイトルで「有効か?」と問いを立てている以上、冒頭は結論から始めるべきです。
それ以外は網羅性も高く、専門性を発揮できそうな構成のため悪くはないと言えるでしょう。
Claude Sonnet 4|Anthropic
評価:
h1:AIライティングはSEOに有効か?2025年最新のGoogle評価基準から見る真実
h2:はじめに:AIライティングの現状とSEO担当者が抱く疑問
h2:AIライティングに対するGoogleの公式見解
h3:Googleが重視するのは「誰が書いたか」より「何が書かれているか」
h3:実際の検索結果データから見えるAIコンテンツの評価
h2:AIライティングのSEO効果:メリットとデメリットを徹底分析
h3:AIライティングの5つのメリット
h4:大量コンテンツの迅速な制作が可能
h4:キーワード最適化の精度が向上する
h4:構造化データの適用がしやすい
h4:多言語対応が容易になる
h4:A/Bテストの効率化が図れる
h3:AIライティングの3つのデメリット
h4:独自性・オリジナリティが不足しがち
h4:情報の正確性にリスクがある
h4:E-E-A-T要素が不足する
h2:SEO効果を最大化するAIライティング活用法
h3:プロが実践する「AI+人間」のハイブリッド手法
h4:Step1:戦略設計は人間が行う
h4:Step2:構成案をAIで作成する
h4:Step3:執筆はAI、編集は人間が担当
h3:効果的なプロンプトテクニックとは?
h2:2025年最新のGoogle評価傾向とAIコンテンツ
h3:Google March 2024 Core Updateがもたらした影響
h3:Helpful Content Updateから読み解く品質基準
h2:業界別AIライティング成功事例
h3:BtoB製造業:技術記事での活用事例
h3:地域密着型サービス業:ローカルSEOでの成功例
h2:AIライティングに関するよくある質問
h3:AIライティングツールはどれを選ぶべき?
h3:AI記事は何割まで使用していいの?
h3:AIコンテンツの著作権問題はどうなる?
h2:まとめ:AIライティングをSEOに活かす5つのポイント「はじめに:AIライティングの現状とSEO担当者が抱く疑問」から始まる点は評価できません。
なぜなら、この記事の訪問者は「AIライティングはSEOに有効か」が知りたいだけで、何の疑問を抱いているかに価値がないからです。
また、内容面でも「Googleが重視するのは『誰が書いたか』より『何が書かれているか』」という表現は間違っています。
GoogleはAIコンテンツを否定していませんが、著者の経験や専門性、信頼性といった「誰が書いたか」に一層重きを置く方向に進んでいます。
また、Googleアップデートの取り上げ方も不十分です。「2024年3月のCore Update」と「Helpful Content Update」だけをピックアップすると限定的すぎて不自然に見えます。
むしろ直近のアップデート全般を俯瞰し、「AI生成コンテンツをどのように評価しているか」という包括的な視点で整理する方が適切です。
さらに事例部分も「地域密着型サービス業におけるローカルSEOの成功例」は、AIライティングの記事としては焦点がずれています。
総合すると、この構成は流れも中身の焦点ずれているという評価です。使用者に知識がないと、誤った情報を発信してしまう可能性があるので注意です。
評価できるポイントは、「よくある質問」のセクションで、AIO対策として有効です。
Gemini 2.5 Pro|Google
評価:
h2:AIライティングはSEOに有効か?【20年間のプロの結論】
h3:結論:AIは「使い方次第」で強力な武器になる
h3:2025年以降、AIとどう向き合うべきか
h2:中小企業がAIライティングをSEOに活用する3つのステップ
h3:ステップ1:AIを「壁打ち相手」に戦略を立てる
h3:ステップ2:AIで「記事の骨子」を作成し、血を通わせる
h3:ステップ3:AIで「分析と改善」のサイクルを高速化する
h2:【事例】AI活用でSEOの成果を上げた中小企業のリアル
h3:事例1:ニッチなBtoB製造業
h3:事例2:地域の工務店
h3:事例3:オンラインショップ
h2:AIライティングの注意点とリスク
h3:AIに「丸投げ」が危険な3つの理由
h3:20年のプロが教えるAIライティングの「やってはいけない」こと
h2:まとめ:AIを「賢い相棒」にして、SEOの新たなステージへこの構成は冒頭で「AIは使い方次第で強力な武器になる」という結論を示しており、読者が最も知りたい答えをすぐに得られる点は非常に良いです。結論ファーストの設計はSEO記事としても読了率を高めやすく、評価できます。
ただし、結論を補強する根拠・理由の見出しが立っていないのはマイナスです。見出し構成だけで読者が内容の7割程度を理解することが理想。
そう考えると、見出しにAIが有効な根拠をいれるべきでしょう。
また「中小企業がAIライティングをSEOに活用する3つのステップ」はフレームとして分かりやすいものの、これだけで実務に直結するレベルかといえば疑問が残ります。
プロンプト設計や検証方法が盛り込まれていないため、実践的価値はやや薄い印象です。
さらに「AIに丸投げが危険な理由」と「やってはいけないこと」は内容が重複しており、分ける必然性が乏しいです。
この部分は統合して「注意点」として整理し、その代わりに「よくある質問(FAQ)」を差し込む方が、読者の検索意図に合致し、記事全体の網羅性も高められます。
Copilot
評価:
h2:AIライティングとは何か?基本から押さえよう
h3:定義と仕組み
h3:代表的なツールとその特徴
h3:人間のライティングとの違い
h2:SEOにおけるAIライティングのメリット
h3:コンテンツ量の拡充とスピード
h3:キーワード最適化の自動化
h3:検索意図に沿った構成の提案
h2:AIライティングのデメリットと限界
h3:オリジナリティの欠如と情報の信頼性
h3:Googleの評価基準との関係
h3:誤情報や偏りのリスク
h2:実際のデータで見るAIライティングの効果
h3:公的機関による調査結果(例:総務省・経産省)
h3:海外の信頼性あるレポート(例:HubSpot, SEMrush)
h3:中小企業での導入事例と成果
h2:SEOのプロが語る:AIライティングは“補助ツール”として活用すべき
h3:一次情報の重要性と人間の役割
h3:E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)との整合性
h3:実務での使い分けと運用ポイント
h2:まとめ:AIライティングはSEOの味方か?敵か?
h3:中小企業が取るべき戦略とは
h3:今後の展望と注意点この構成は「AIライティングの定義 → メリット → デメリット → データ → プロの見解 → まとめ」と、一見すると整然と並んでいて“まとまり感”があります。
しかし、実際にはユーザーが知りたい「AIライティングはSEOに有効か?」という結論の回答がありません。つまり 一見まとまってそうな流れ でありながら、読者の疑問解決していない見出し構成といえます。
最後まで「結論=SEOに有効なのか?」が提示されず、まとめでも「味方か?敵か?」という曖昧な問いかけで終わっています。
さらに、読者が本当に知りたいのは「「SEOに有効か?」」ではありません。このテーマの潜在的な検索意図は「有効ならどう使えばいいか」です。
調査結果や事例を厚めに入れている一方で「ではどう使えばいいのか」という方法論が欠落しており、読者の検索意図に応えられていません。
良い点をあげるなら、公的機関や海外の信頼できるレポートを根拠として盛り込んでいること。これはSEO上の権威性を高める上で評価できる部分です。
Genspark
評価:
h2:AIライティングのSEO効果:最新データが示す実力
h3:85%が効果を実感した調査結果
h3:AIツール市場の急成長が証明する有効性
h3:コンテンツ品質への高い評価
h2:GoogleはAIコンテンツを排除していない真実
h3:Google公式ガイダンスの明確な見解
h3:E-E-A-T評価基準とAIコンテンツの関係
h3:2024年アルゴリズム更新の本当の意味
h2:中小企業が実感するAIライティングの効果
h3:導入目的トップ4と期待効果
h3:ROI向上の具体的成功事例
h3:コスト削減効果の実測データ
h2:SEO効果を最大化するAIライティング活用法
h3:品質向上のための必須3ステップ
h3:オリジナリティ追加のポイント
h3:避けるべきNG使用方法
h2:効果的なAIライティングツールの選び方
h3:中小企業向けツール選定基準
h3:SEO機能の重要性ランキング
h3:導入時の段階的アプローチ方法
h2:2025年SEOトレンドとAIライティングの未来
h3:Googleアルゴリズム進化への対応策
h3:AI活用拡大予定企業56.4%の意味
h3:競合優位性確保のための戦略
h2:まとめ:データが証明するAIライティングのSEO有効性この構成は データ・事例・ツール選定・未来予測までをカバーしており、読者の求める内容の網羅性は高いです。
特に「85%が効果を実感」「AIツール市場の急成長」といった数値を活用して説得力を高めている点は、読者の信頼を獲得しやすく評価できます。さらに、未来のトレンドやGoogleアルゴリズムの進化に触れている点も良いです。
ただし、悪い点も目立ちます。
まず、対象読者を「AIライティングがSEOに有効か」を調べている読者を想定すると、恐らく「マーケティングにまだ明るくない方」でしょう。
そう考えると、見出しの「ROI」などの用語はレベル感が合わない可能性があります。専門的すぎる言葉遣いは読者層に合わせてかみ砕くべきでしょう。
また、見出しの構造は一見しっかりしているものの、見出しを読んだだけで記事全体の70%を理解できるレベルには達するのが理想です。
たとえば「Google公式ガイダンスの明確な見解」という見出しも、「Google公式ガイダンスは〇〇な見解」とすることで、見出しだけで内容が理解できます。
【まとめ】生成AIごとの見出し構成の比較
今回は5つの生成AIに「AIライティングはSEOに有効か」というテーマで同じプロンプトを与え、見出し構成を比較しました。
今回のテーマに関しては、結果は以下の通りでした。
| ツール | 星評価 |
|---|---|
| ChatGPT | |
| Claude Sonnet 4 | |
| Gemini 2.5 Pro | |
| Microsoft Copilot | |
| Genspark |
結果として、どの生成AIも無料プランで思ったよりも使えました。特に今回に限っては、「Gemini 2.5 Pro」「Genspark」がもっとも優秀。
しかし、最後は自分で手直しする必要があるというのが正直な感想です。
複数の生成AIを並べて比較したことで、各ツールの特徴と欠点が浮かび上がりました。
たとえば、結論ファーストはGeminiが得意、データ重視はGenspark、実践ガイドはChatGPTといった具合です。
最終的にはこれらの生成AIが作った見出しを組み合わせ、最適な流れに編集することがおすすめです。
それぞれの生成AIで違う結果がでることで、自分の中に不足していた着眼点を教えてくれるのも助かるポイントでした。
【完成形】手直しした見出し構成
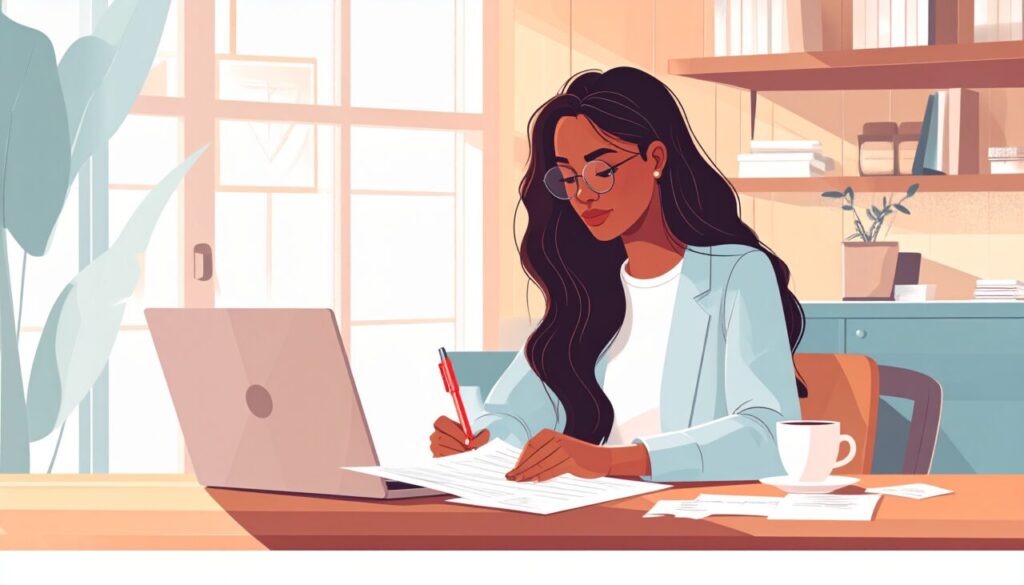
ここまでの生成AIが作成した見出しを踏まえて、最後はご自身の手で修正することがクオリティアップには肝心です。
最後に、手直しした見出し構成と、気を付けたポイントを整理させていただきます。
手直しして完成させた見出し構成
テーマ「AIライティングはSEOに有効か」
h2:結論:AIライティングは「使い方次第」でSEOに有効
h3:AIは補助ツールとして活かすのが正解
h3:Google公式ガイダンスはAIを「排除しない」と明言
h3:人間の専門性と掛け合わせてこそ成果が出る
h3:誤用すると逆効果になるリスクもある
h2:AIライティングの成果・事例紹介
h3:85%が効果を実感した調査データ
h3:海外レポート(HubSpot・SEMrush等)が示す検索順位への影響
h3:導入事例と成果(当社事例)
h2:おすすめのAIライティングツール
h3:ツールA
h3:ツールB
h3:ツールC
h2:SEOに活用する3つのプロンプト
h3:戦略を立てるための「壁打ちプロンプト」
h3:記事構成を設計する「骨子作成プロンプト」
h3:改善点を見つける「分析・リライトプロンプト」
h2:AIライティングの注意点とリスク
h3:一次情報がない記事はSEOで評価されない
h3:誤情報による信用失墜リスク
h3:重複コンテンツ扱いされる可能性
h3:引用・出典を明示しないと著作権違反のリスク
h2:AIライティングに関するよくある質問(FAQ)
h3:AI記事はどこまで使っていいの?
h3:著作権や法的リスクはあるの?
h3:検索順位は本当に上がるの?
h3:質問
h2:まとめ:AIを「賢い相棒」にしてSEOの成果を伸ばそう見出し修正時に気を付けたポイント
この見出しを作る際に気を付けたポイントを整理しました。
- 冒頭で結論を提示
「AIライティングは使い方次第でSEOに有効」と明確に答える。
ユーザーが知りたいことを最初に示すことで、離脱を防ぎ読了率を高める。 - 結論を補強する多面的視点
Googleの公式立場やE-E-A-Tとの関係、人間の専門性との掛け合わせを提示。
「有効だがリスクもある」というバランスを保ちながら、信頼できる説明を展開。 - データと事例による裏付け
調査データ、海外レポート、自社事例を配置。
数字や具体的事例で説得力を高め、単なる意見で終わらない構造になっている。 - 実務に直結する活用法
おすすめツール紹介 → 3つのプロンプト活用法と、すぐ使えるノウハウを提供。
「SEOに有効ならどう使えばいいか」という検索意図に的確に応えている。 - リスクを具体的に明示
一次情報不足、信用失墜リスク、重複コンテンツ、著作権問題を整理。
実際に起こり得る失敗を明示し、リスク回避のための指針を与えている。 - FAQで読者の疑問をカバー
「どこまで使える?」「著作権は?」「順位は本当に上がる?」といった実務上の疑問に答える。
検索意図を広く拾い、記事全体の網羅性を補完。 - 前向きなクロージング
「AIを賢い相棒にしてSEO成果を伸ばそう」とポジティブに締める。
リスクを伝えた上で希望を持たせ、CTAにつなげる。
まとめ
本記事では、無料で記事作成に使える生成AI5種(ChatGPT/Claude Sonnet 4/Gemini 2.5 Pro/Copilot/Genspark) を同一条件で比較し、見出し構成を検証しました。
結論としては、いずれの生成AIも無料で十分使えるレベルですが、そのまま使うのは難しいです。
今回のように、複数の生成AIで同じ指示を与えることで、それぞれの良い点・悪い点が見えてきます。
最終的に、それぞれの良い点だけを集めて、人間による編集を加えるのが理想的ということがわかりました。
とはいえ、いくらAIを上手に活用しても、最終的に仕上げる人間の経験と実力が問われるのも事実です。
もし「AIを活用して記事を書きたいけど、自分で仕上げる自信がない」「戦略設計から記事制作まで丸ごと任せたい」と思われたら、ワールドリンクにお気軽にご相談ください。500以上の検索キーワードで検索1位をとったライティングの代行も承っています。どうぞお気軽にご相談ください。
また、今回は記事の本文まで作成しませんでしたが、別の記事で本文の比較を行いますのでそちらも併せてみていただけると嬉しいです。(近日公開)



